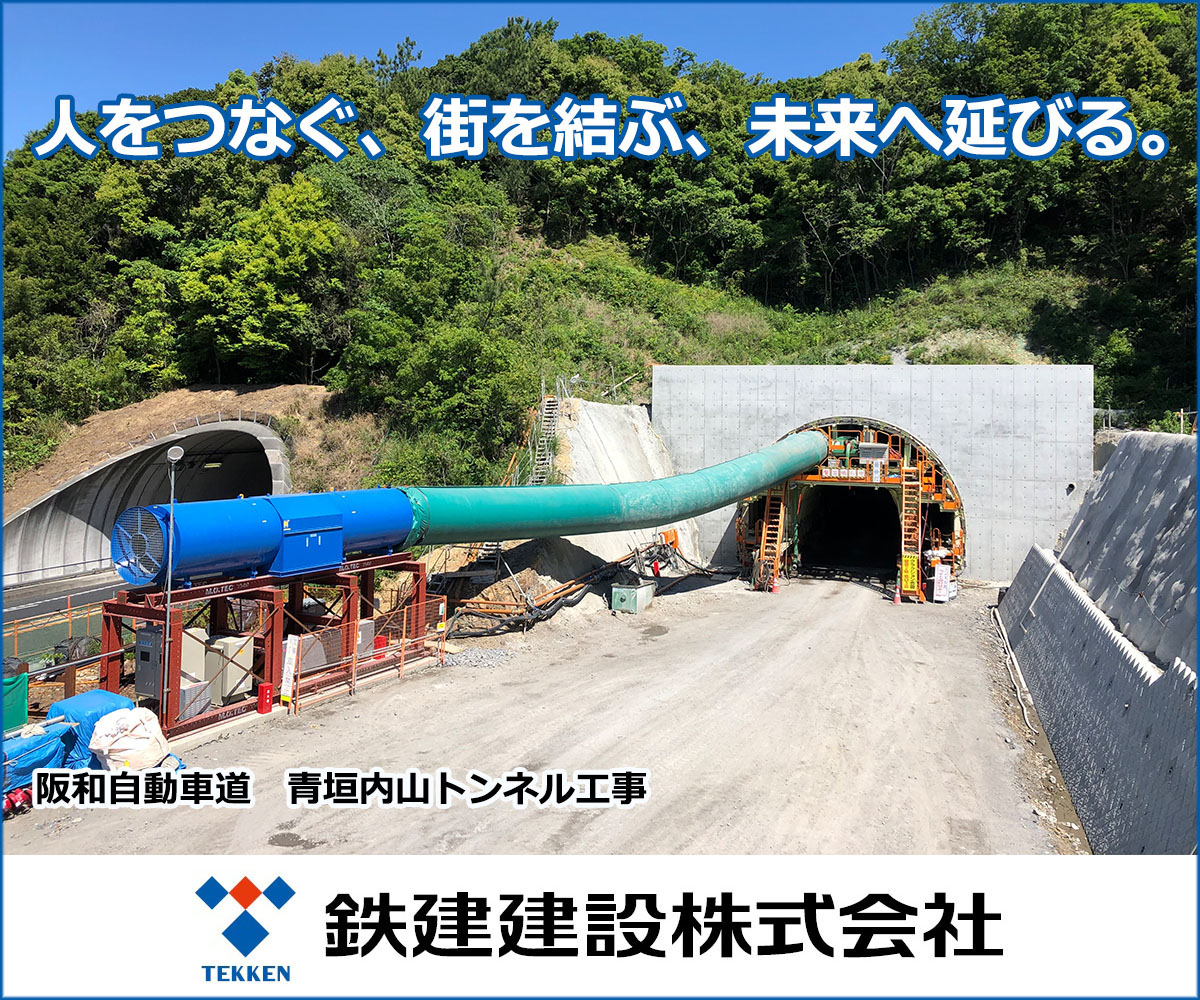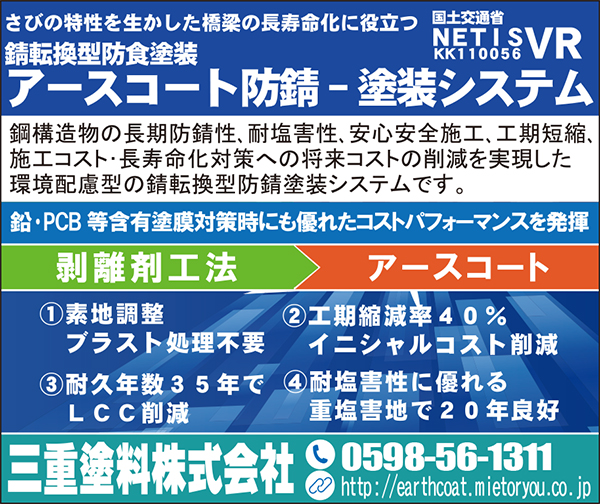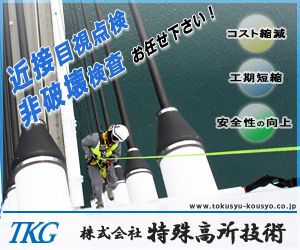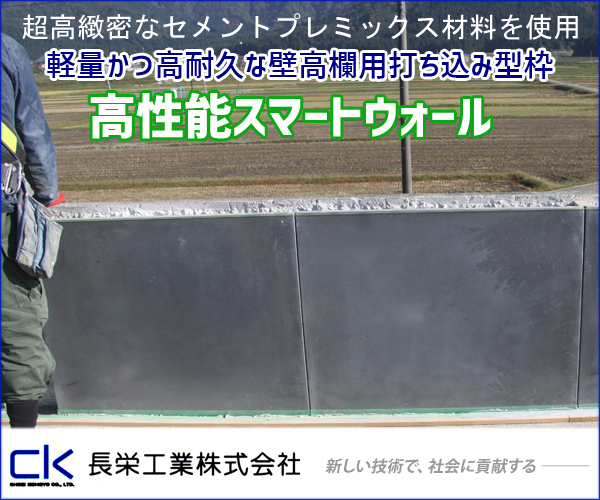-分かっていますか?何が問題なのか- 第54回 自碇式吊橋・清州橋と田中豊 ~新たな物事にチャレンジする意欲を実らせるには~
これでよいのか専門技術者
2.国の重要文化財・清洲橋とピッツバーグの自碇式吊橋群
清洲橋は、大正関東地震の震災復興事業で東京都心を流れる隅田川(旧荒川)に架けられた橋梁である。一方、葛西橋は、「荒ぶる川」荒川(東京府・市エリアは隅田川)の洪水被害を解消する目的で計画された放水路建設事業によって造られた、『荒川放水路』の河口近くに架かる橋梁である。今回は、都心を流れる隅田川に架かる写真‐3に示す国の重要文化財・清洲橋について話を進めよう。
本文を始める前に、何故私が清洲橋の話を読者にしたくなったのか、私自身も忘れていしまったので思い起こしてみよう。話は昨年の9月1日号『新たな構造、形式にチャレンジするには』に遡る。私がその時話したポイントは二つある。一つは、大学における教員の指導法に関する話であり、もう一つは、技術者が新たな構造や工法を考案し、採用する際に行う手法についてであった。第一の学生指導法、講義科目の修得度、理解度であるが、教員の教育方法に関する考え方で大きな差異が生まれる。私も縁あって、大学の教壇に立ち始めて10年を超えたが、何を今更と怒られるかもしれないが、未だ教員としては半人前、指導法には全く自信がない。このような自分を叱責する意味もあって、講義手法の基本をおさらいする気持ちで、私にとって課題となっていた『構造』を如何に学生に理解させるかについて取り上げた。
2.1 構造力学の指導法と人材育成
大学の講義科目には種々あるが、橋梁に関係する技術を修得するうえで、必ず学ばなければならない科目が『構造力学』もしくは『応用力学』である。なぜ、『構造力学』、構造系の学生多くが興味を示すことのない当該科目の必要性は本連載の後半分部で、事例を持って話をしよう。まずその前に『構造力学』の講義内容は、作用力(力、力の合成、つり合い)から始まり、モーメント、梁の外力、梁の内力、材料の強さ、梁に発生する応力、梁のたわみから影響線などを教え、安全・安心な構造物を造る基礎の修得が到達点であったと思う。当然私も大学では、必須科目であり、学科主任の強い勧めもあって『構造力学』を選択し、意欲満々の状態?で講義を受けることになった。しかし、講義が3回目、4回目と進むに従い、講義に対する自らのモチベーションは急降下し、睡魔との戦いが主となっていった。現在の私であったらどうであろう。
教壇で、『構造力学』の要点や、事例を含めて解説する教師の発言に耳を大きく開き、要点を示す板書に眼は釘付け、必死にメモを取るであろう。学生時代と今では一体何が違うのであろう。それは、自分の目標が朧気ながらの橋から道路橋のメンテナンス・マネジメントと明確になり、その目標の中で成果をあげるには、関連する知識と技術を修得することが絶対条件であると知ったからである。学生に対する教育、社会人に対する研修、いずれもモチベーションを上げることが必要となる。それには、受講者に対し、選択する科目の重要度、科目内容を修得することによって得られる成果を明確にし、それを理解させることが重要である。ここまで偉そうなことを言っている私の学生時代、担当教師の私への『構造力学』修得度評価は芳しいものではなく、評価点は低空飛行状態であったと記憶している。ここまで読まれた読者から、「何だ、いつもの舌先三寸!偉そうなことを言っても、ほら、中身がないではないか」と影の声が聞こえてくる。その事実を物語るのが、以前私がお話しした『高欄の設計』の話である。一般的な学力があればだれでもできる、『高欄の設計』に四苦八苦したのは、学生時代に必要最低限の基礎知識を修得しなかったことが問題で、筆者の『学び』に対する不真面目さが第一の原因なのだが。私の話を読んだ読者もそう思っている、確かにその通りである。しかし私は、読者の私に対する評価が落ちるのは百も承知で話を続ける。私の場合『構造力学』を修得すると社会人になって何に役立つのか、そのイメージが頭の中で全く湧かなかったからである。
半年前に話したが、私が感心した学生指導法は、社会人研修にも通ずると確信する日本大学理工学部の山崎淳教授(今は退官され北海度に住まわれている)の指導法である。ここでもう一度その指導法のポイントを紹介しよう。それは、学生に『構造力学』、特に橋梁構造を理解させるには、身近な橋梁をモデルにして縮小タイプの模型を製作させ、まずはその模型に力を加えるとどこの部材がどのように変形するのを確認させる。次に、自分で作ったモデルの破壊形態をイメージさせ、イメージを基に力を増やした時、イメージ通りに破壊するか否か、何が違っているかを学ばせる。学生に、机上で学んだ『構造力学』の作用力と材料の強さ、部材の変形などが実体験で分かるという考えだ。特に学生が目を輝かせるのは、自分の目で見ることができる著名な橋梁をモデルに製作した模型を破壊する時だそうだ。
私も山崎先生の指導法で学んでいれば、先の高欄の設計なんか『お茶の子さいさい』であったであろう。自分の目で見て、直接肌で触ることのできる構造物を対象に、グループで写実的な模型を製作し、その模型を使って『構造力学』真の『橋梁工学』を学ばせる指導法である。『サルでも分かる・・・』ではないが、これなら分かる。身近の構造物が対象となっているので親近感もわき、実に分かり易い。その実橋梁の事例としたのが、東京・隅田川に架かる世界に誇る著名橋・清洲橋であった。前置きが長くなったが、いよいよ待ちに待った清洲橋の話しである。
2.2自碇式吊橋の原点、吊橋とニューヨークの3橋
清洲橋の構造形式は、読者も知っている吊橋の一種、自碇式吊橋である。そもそも吊橋の原形は、太古時代、山間の谷を渡る猿から学び、天然の藤や蔓を使った吊形式の橋もど きで架けられところから始まる。その後、吊橋に使われる材料や形は変われども、人々は経験則のような考え方で吊橋を架けていた。現在の長大な支間長に架かる吊橋に発展するのは19世紀後半で、吊材も鉄鎖からアイバーチェーン(写真‐4参照)、そしてワイヤーケーブルと材料が進歩する。その後、使用材料も強度の高い材料へ、そして吊橋設計法も確立されていく。長大吊橋建設の進む米国や欧州において、吊橋の実用設計の理論が普遍化され、急速に進歩していった。吊橋設計の当初は、桁橋やアーチ橋などで使われる桁のたわみ変形を考慮しない、弾性理論や均等分配理論を近似解法として採用している。それは吊橋、中でも吊橋の桁、補剛桁を剛構造と考える弾性理論の登場である。
きで架けられところから始まる。その後、吊橋に使われる材料や形は変われども、人々は経験則のような考え方で吊橋を架けていた。現在の長大な支間長に架かる吊橋に発展するのは19世紀後半で、吊材も鉄鎖からアイバーチェーン(写真‐4参照)、そしてワイヤーケーブルと材料が進歩する。その後、使用材料も強度の高い材料へ、そして吊橋設計法も確立されていく。長大吊橋建設の進む米国や欧州において、吊橋の実用設計の理論が普遍化され、急速に進歩していった。吊橋設計の当初は、桁橋やアーチ橋などで使われる桁のたわみ変形を考慮しない、弾性理論や均等分配理論を近似解法として採用している。それは吊橋、中でも吊橋の桁、補剛桁を剛構造と考える弾性理論の登場である。
弾性理論で設計・架設されたのが、読者の多くが知っている米国では世界初の吊橋鉄道橋であったナイアガラ橋(Niagara Bridge・1855年~1897年)や道路橋のブルックリンブリッジ(Brooklyn Bridge・1883年)である。時代はより長い橋を容易に、そして安全に架けたいとのニーズが高まると同時に、計画する橋長も長くなり、当然支間長も長くなる。吊橋のケーブルも桁も一体として変形し、作用する荷重に対して抵抗する、吊橋本来の長所を重視して設計しようと考えるようになる。その結果、従来からある弾性理論によって長大支間長の吊橋を設計すると、無駄が多いことにも徐々に気づき始めた。従来の弾性理論による吊橋設計を適用できるのは、支間長が100mから200m程度であるとの結論に至ったのである。その理由は、支間長が400m以上になると桁のたわみ変形は当然大きくなるが、弾性理論によって設計すると桁断面が大きくなりすぎるからだ。このような理由から、鉛直荷重に対して吊橋のケーブルと桁が一体となって変形すると考える、撓度理論が 考え出された。撓度理論は、桁の変形を考慮する非線形解析理論であることから、桁に発生する断面力を低減でき、補剛桁の断面を減らすことが出来る。これまで弾性理論と比較し、長大吊橋設計に優位な撓度理論を最初に使って設計されたのが、『deflection theory』で有名なレオン・モイセイフ(Leon S. Moisseiff)のニューヨーク・マンハッタンブリッジ(Manhattann Bridge)である。レオン・モイセイフの考えは、「橋が長くなれば長くなるほど柔軟にすることができる」に代表され、彼は有名なサンフランシスコのゴールデンゲート橋(写真‐5参照)の設計にも関与している。
考え出された。撓度理論は、桁の変形を考慮する非線形解析理論であることから、桁に発生する断面力を低減でき、補剛桁の断面を減らすことが出来る。これまで弾性理論と比較し、長大吊橋設計に優位な撓度理論を最初に使って設計されたのが、『deflection theory』で有名なレオン・モイセイフ(Leon S. Moisseiff)のニューヨーク・マンハッタンブリッジ(Manhattann Bridge)である。レオン・モイセイフの考えは、「橋が長くなれば長くなるほど柔軟にすることができる」に代表され、彼は有名なサンフランシスコのゴールデンゲート橋(写真‐5参照)の設計にも関与している。
それでは、過去の設計理論(弾性理論)と現在に通ずる設計理論(撓度理論)で設計した場合、どのような差異が生ずるのかを実橋で確認してみよう。この2つの設計法の違いを確認できる題材が身近にある。それも、私が何度も訪れている魅力ある街、ニューヨーク・マンハッタンにある。それは、マンハッタンの東側を流れるイーストリバーに架かる3橋なのだ。ここで、私が現地で撮ってきたイーストリバーに架かる3橋、河口からブルックリンブリッジ、マンハッタンブリッジ、ウィリアムズバークブリッジの違いを写真で見てみよう。
 図‐2は、米国、ニューヨーク州ニューヨーク市を流れるイーストリバーと3橋の位置を示している。話は全く違うが、最近、新型コロナウィルス感染の報道では、ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモ氏の方が圧倒的にテレビ等への出番が多く、ニューヨーク市長ビル・デブラジオ氏は影が薄い。以前は、ニューヨーク市の市長の方が報道に取り上げられる場面が多く、例えば、デイヴィド・ディンキンスやルドルフ・ジュリアーニ、マイケル・ブルームバーグなど、いずれも読者の多くが耳にしたことのある著名人である。現ニューヨーク市長・ビル・デブラシオ氏の政策理念や施策に関する注目度が低いのか、ニューヨーク市職員の行政意欲が薄れたのか、いずれにしても市長の影が薄いようでは心配だ。その理由は、これまで、ニューヨーク市交通局には、私が優れた行政技術者と感動したサミェル・シュワーツや蜘蛛男の異名で名高いヤネフが技監として管理橋の維持管理に目を光らせていた。当然、ここに挙げた技監の提案する予防保全型管理に同意し、当時の市長自らの政策として公表してきた橋梁管理の戦略が衰退し、数多くある著名な橋梁もメンテナンス不足になるのではと心配だ。
図‐2は、米国、ニューヨーク州ニューヨーク市を流れるイーストリバーと3橋の位置を示している。話は全く違うが、最近、新型コロナウィルス感染の報道では、ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモ氏の方が圧倒的にテレビ等への出番が多く、ニューヨーク市長ビル・デブラジオ氏は影が薄い。以前は、ニューヨーク市の市長の方が報道に取り上げられる場面が多く、例えば、デイヴィド・ディンキンスやルドルフ・ジュリアーニ、マイケル・ブルームバーグなど、いずれも読者の多くが耳にしたことのある著名人である。現ニューヨーク市長・ビル・デブラシオ氏の政策理念や施策に関する注目度が低いのか、ニューヨーク市職員の行政意欲が薄れたのか、いずれにしても市長の影が薄いようでは心配だ。その理由は、これまで、ニューヨーク市交通局には、私が優れた行政技術者と感動したサミェル・シュワーツや蜘蛛男の異名で名高いヤネフが技監として管理橋の維持管理に目を光らせていた。当然、ここに挙げた技監の提案する予防保全型管理に同意し、当時の市長自らの政策として公表してきた橋梁管理の戦略が衰退し、数多くある著名な橋梁もメンテナンス不足になるのではと心配だ。
話は戻して、イーストリバー河口に近い、ニューヨーク市のゲート、市民が愛してやまないブルクリンブリッジ(写真‐6参照)を見てみよう。写真‐7は、弾性理論によって設計されたブルクリンブリッジの補剛桁である。次に、現在も地下鉄が通行している河口から2番目の橋、ブルックリンブリッジに近接するマンハッタンブリッジ(写真‐8参照)を見てみよう。写真‐9は、撓度理論によって設計されたブルクリンブリッジの補剛桁である。確かに、補剛桁を構成している部材の違いと桁高の違いは明らかで、両橋が近接していることから対比することが容易で、面白い。
 次に、先にあげた2橋とは少し離れた位置に架かる、3番目の橋、ウィリアムズバークブリッジ(写真‐10参照)である。ウィリアムズバークブリッジは弾性理論で設計されていることは述べたが、補剛桁を見ると、ブルックリンブリッジに設計理論が同じであることが分かるし、当然のように補剛桁の桁高も結構高い。私自身も、ここに挙げた架設年次の異なる3橋は、先に示した2つの理論を使い分けていると聞いて知っているので、いつも対比して見ることにしている。しかし、美しいこの3橋の桁下を通過するたびに、弾性理論と撓度理論の違いを思わず口にしたくなる橋オタク??である第一の自分に対し、反旗を翻す第二の自分が「全く色気がない、マニアックだな!早く脱皮しろよ」と囁くのはいつものことである。自碇式吊橋の話をする前に、その原点である吊橋の話を長々としたが、ここで、自碇式吊橋・清洲橋の話に戻すとしよう。
次に、先にあげた2橋とは少し離れた位置に架かる、3番目の橋、ウィリアムズバークブリッジ(写真‐10参照)である。ウィリアムズバークブリッジは弾性理論で設計されていることは述べたが、補剛桁を見ると、ブルックリンブリッジに設計理論が同じであることが分かるし、当然のように補剛桁の桁高も結構高い。私自身も、ここに挙げた架設年次の異なる3橋は、先に示した2つの理論を使い分けていると聞いて知っているので、いつも対比して見ることにしている。しかし、美しいこの3橋の桁下を通過するたびに、弾性理論と撓度理論の違いを思わず口にしたくなる橋オタク??である第一の自分に対し、反旗を翻す第二の自分が「全く色気がない、マニアックだな!早く脱皮しろよ」と囁くのはいつものことである。自碇式吊橋の話をする前に、その原点である吊橋の話を長々としたが、ここで、自碇式吊橋・清洲橋の話に戻すとしよう。
2.3自碇式吊橋・スリーシスターズ3橋と清洲橋
1909年に撓度理論によるマンハッタンブリッジが完成した同じ時代に、橋梁の新たな構造形式を追求していたドイツでは、清洲橋に採用した構造形式、長大吊橋にはあるアンカレイジの無い、すっきりした外観の自碇式吊橋が考案された。自碇式吊橋として著名なのは、1913年から1915年にかけてドイツのルーベック、ケルンのライン川に架けられた『Deutz Suspension Bridge(ドイツ名:Deutzer Hängebrücke、後の1935年にHINDENBURG橋と命名された)』である。吊り材は、この後説明するピッツバーグのスリーシスターズと呼ばれている3橋や清洲橋と同じ、先に清洲橋に使っている同タイプの鋼アイバーチェーン材を使っていた。今は無き『Deutz Suspension Bridge』の規模は、中央径間184m、側径間92m、総幅員27.5mであった。
『Deutz Suspension Bridge』を見て、吊橋特有の巨大なアンカレイジの無い、橋台の部分がすっきりした外観に魅せられたのは、清州橋の提案者である田中豊だけではなく米国の橋梁技術者も同様であった。ドイツで考案された自碇式吊橋を米国に持ち込んだのは、異論もあるがヴァーノンR.コヴェル(Vernon R. Covell)であると私は思っている。その理由は、ペンシルバニア州・ピッツバークに1926年から1928年の短期間にアレゲニー川にスリーシスターズと呼ばれている3橋(図‐3参照)を架設した資料の詳細と現地ピッツバー グで並行して架かる3橋を見た時、何となくインスピレーションを感じ、それ以降ヴァーノンR.コヴェルであると思っている。なんと、ヴァーノンR.コヴェルアは、レゲニー郡公共工事局(Allegheny County Public Works Departmen)に勤務する行政技術者であるのだ。彼は、橋梁だけでなく、トンネル(Armstrong Tunnel・ピッツバーグほか)にも、主任技術者としてその名前を残している。実に素晴らしい。その昔は、日本にも、原口要、倉田吉嗣、原龍太、樺島正義、田中豊、増田淳、そして前号で紹介した亡き吉田巌さんなど、優れた行政技術者は数多く育っている。
グで並行して架かる3橋を見た時、何となくインスピレーションを感じ、それ以降ヴァーノンR.コヴェルであると思っている。なんと、ヴァーノンR.コヴェルアは、レゲニー郡公共工事局(Allegheny County Public Works Departmen)に勤務する行政技術者であるのだ。彼は、橋梁だけでなく、トンネル(Armstrong Tunnel・ピッツバーグほか)にも、主任技術者としてその名前を残している。実に素晴らしい。その昔は、日本にも、原口要、倉田吉嗣、原龍太、樺島正義、田中豊、増田淳、そして前号で紹介した亡き吉田巌さんなど、優れた行政技術者は数多く育っている。
なぜ、近年、行政技術者に優れたプロフェッショナルエンジニアと呼ばれる技術者が存在しなくなったかは、別の機会に譲るとして、話を自碇式吊橋に戻すとしよう。アレゲニー川に近接して架かる3橋で最初に架設されたのが、1926年6月のAndy Warhol Bridge(Seventh Street Bridge)、2番目が1926年11月のRachel Carson Bridge(Ninth Street Bridge)、そして最後が一番有名な大リーグ・ピッツバーグパイレーツの本拠地で あるPNCパーク野球場に最も近い、他の2橋より2年遅れ1928年10月架設の図‐4に示すRoberto Clemente Bridge(Sixth Street Bridge)である。スリーシスターズ3橋を設計したヴァーノンR.コヴェルアと清洲橋を設計した田中豊とは、考え方がとても良く似ている。その理由は、お手本となったドイツ・ケルンの『Deutz Suspension Bridge』は補剛桁の内側に歩道と車道があるが、米国の3橋も日本の清洲橋も歩道を外側に出している。しかし、ピッツバーグのスリーシスターズ3橋は当然外観も詳細構造も清洲橋に似てはいるが、ベースは同じでもよく見るとかなり違いがある。アイバーチェーン吊り材の補剛桁への収まり、主塔と支承の構造など、図‐5と図‐6に示したので清州橋を思い浮かべて、何故私の言う違いがあるのかを考えてほしい。
あるPNCパーク野球場に最も近い、他の2橋より2年遅れ1928年10月架設の図‐4に示すRoberto Clemente Bridge(Sixth Street Bridge)である。スリーシスターズ3橋を設計したヴァーノンR.コヴェルアと清洲橋を設計した田中豊とは、考え方がとても良く似ている。その理由は、お手本となったドイツ・ケルンの『Deutz Suspension Bridge』は補剛桁の内側に歩道と車道があるが、米国の3橋も日本の清洲橋も歩道を外側に出している。しかし、ピッツバーグのスリーシスターズ3橋は当然外観も詳細構造も清洲橋に似てはいるが、ベースは同じでもよく見るとかなり違いがある。アイバーチェーン吊り材の補剛桁への収まり、主塔と支承の構造など、図‐5と図‐6に示したので清州橋を思い浮かべて、何故私の言う違いがあるのかを考えてほしい。
その後、ドイツ、米国、そして日本と自碇式吊橋を採用する事例はうなぎ上りになったかというと、そうはならなかった。自碇式吊橋は、米国ではスリーシスターズ3橋が架けられて以降、日本では清州橋を架けて以降、中小橋梁を除いてこの形式を採用する事例は 無かった。これは、建設時に必要な支保工や桟橋の複雑さなどが災いしたようである。その理由が読者にも分かるように、清州橋の架設工事から、架設順序を示す図‐7に示した。また、清州橋架設工事における、仮設の桟橋、架設構台、支保工などを使った上部工・補剛桁架設状況を図‐8に示した。自碇式吊橋とは、Self-anchored suspension bridgeでお分かりのように主索に作用する張力と補剛桁の軸力がつり合った構造的特徴がある。このようなことから、自碇式吊橋は長大吊橋に採用するのは無理であるが、完成形を考えると中規模の吊橋には利点は多い。自碇式吊橋のメンテナンスを考えても、
無かった。これは、建設時に必要な支保工や桟橋の複雑さなどが災いしたようである。その理由が読者にも分かるように、清州橋の架設工事から、架設順序を示す図‐7に示した。また、清州橋架設工事における、仮設の桟橋、架設構台、支保工などを使った上部工・補剛桁架設状況を図‐8に示した。自碇式吊橋とは、Self-anchored suspension bridgeでお分かりのように主索に作用する張力と補剛桁の軸力がつり合った構造的特徴がある。このようなことから、自碇式吊橋は長大吊橋に採用するのは無理であるが、完成形を考えると中規模の吊橋には利点は多い。自碇式吊橋のメンテナンスを考えても、 さほど手間がかかるわけでもないので、ぜひ採用したいと考えたくもなる。しかし、図‐7、図‐8で示したように、自碇式吊橋の大きなマイナスポイントは、施工が複雑で、仮設設備の多さに難点があるのだ。次に、国内唯一の鋼自碇式吊橋の採用に踏み切った田中豊大学名誉教授(これ以降、田中豊)の話をしよう。
さほど手間がかかるわけでもないので、ぜひ採用したいと考えたくもなる。しかし、図‐7、図‐8で示したように、自碇式吊橋の大きなマイナスポイントは、施工が複雑で、仮設設備の多さに難点があるのだ。次に、国内唯一の鋼自碇式吊橋の採用に踏み切った田中豊大学名誉教授(これ以降、田中豊)の話をしよう。