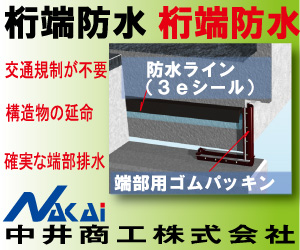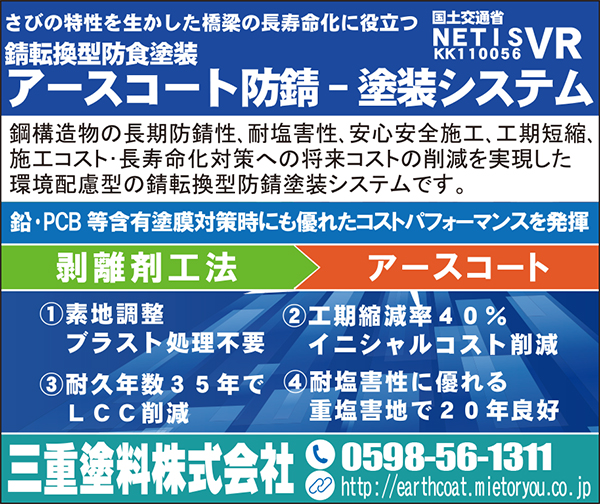-分かっていますか?何が問題なのか- ㊺高齢橋梁の性能と健全度推移について(その2)‐将来に残すべき著名橋になすべきことは‐
これでよいのか専門技術者
2. 重要文化財・永代橋の耐力は現代にも通ずるか?
1970年(昭和45年)、永代橋に行った載荷試験の概要を再度説明し、本論に移るとしよう。実橋載荷試験は、静的載荷試験と動的載荷試験とを分けて行い、8トントラックに砂利を満載、総重量16トンの荷重車を10台準備し、使い分けている。静的載荷試験は、1/4ℓ、1/2ℓ、3/4ℓ点に対して橋軸直角方向に対称載荷するだけでなく、両側に偏心載荷等も行った。また、床組に対しては、部分的な特殊載荷も行っている。載荷試験はそれぞれ3回行い、測定精度が高まるように配慮したようだ。動的載荷試験は、対象橋梁の振動特性を調べる目的である。そこで、静的載荷試験で使った荷重車2台を車道の中心を並列して走行させる対称走行と、2台を橋軸方向に直列して車道を偏心して走行させる方法によって計測した。なお、荷重車の走行速度は、10㎞、20㎞、30㎞、40㎞の4種類を3回行っている。載荷試験は、ここまで説明した方法以外に、荷重車1台の後輪を台上20㎝から落下させる落下試験と、荷重車を急停止させて橋梁の減衰状態を計測する方法も行っている。今から約50年前に、今回説明している載荷試験を主要幹線に架かる橋梁に行った事は、当時の技術者の先進性には驚きである。今回行った載荷試験の測定位置図(下流側)を図‐7に示した。なお、今回の連載は、技術的解説資料ではないので、測定位置も下流側のみとし、上流側の測定位置図等は省略した。それでは、皆様お待ちかねの本題と言える永代橋の載荷試験について、後段を説明しよう。
2-1主構造の応力度
支間中央の橋軸直角方向に、荷重車10台を均等載荷した時(L1)の中央径間アーチリブ主構の計測結果を図‐8に示す。L1載荷は静的載荷試験で2回行った。載荷試験によるアーチリブ箱桁(図‐7のアーチリブ1-2点)の計測結果は、上フランジが理論値-125㎏/㎠に対し実測値は65.6%の-82(二回目-107)㎏/㎠、穴あき下フランジが理論値90㎏/㎠に対し実測値は70.0%の63(二回目55)㎏/㎠であった。
荷重車の載荷位置を支間中央で下流側に路肩から1.55m離れた位置に一列4台、それに平行するように4台、合計8台を偏載荷した場合(L5載荷)の1-2点の計測結果は、箱桁上フランジは理論値-128㎏/㎠に対し実測値は62.5%の-80(二回目-107)㎏/㎠、穴あき下フランジは理論値79㎏/㎠に対し実測値は50.6%の40(二回目34)㎏/㎠となった。なお、L5載荷の1-2点の計測結果図は省略する。
次に、前述と同様に支間中央にL-1載荷した場合の、支間中央1-2点から右岸側に移動したアーチリブ主構1-3点(図-7参照)の計測結果は、箱桁上フランジは理論値-53㎏/㎠に対し実測値は71.7%の-38(二回目-38)㎏/㎠、穴あき下フランジは理論値㎏-2kg/㎠に対し実測値は250.0%の-6(二回目-5)㎏/㎠となった。L-1載荷の1-3点の計測結果図も一回の連載分量を考え省略する。結論としては、載荷実験によって得られた実測値は何れも理論値(計算値)よりも低く、作用荷重による該当部材の発生応力が一致することは無く、15%~30%程度少ない値となった。ここに示した実測値と理論値の差異は、私の数少ない載荷試験結果と同様で、構造形式や規模が異なった橋梁の場合でも同様な傾向で、実橋が実荷重に対し余力があることを示している。以上が、私が着目したアーチリブ中央位置の載荷試験結果である。
2-2 固有振動数
現在であれば、振動数も波形も容易に記録を残せるが、当時は一部を除いて測定器具やデータ記録保存装置などが十分でなかったことから目視による読み取りによる手法であった。永代橋の実橋計測も後者の範囲内で行われ、今回示すのは自由減衰波以外の記録であることを認識して貰いたい。今回載荷試験によって計測された固有振動数やモード図は、橋梁上を車両が走行中の記録から周期を読み取り、測定波の中から卓越していると考えられる波形に着目、周期としている。記録から得られた周期を見ると、起振方法の種別に関係なく概ね0.3sec~0.4secに間に位置している。またモード図を見ると、起振方法に関係なく図‐9に示すような波形が数多く見られた。
静たわみと比較して動たわみの絶対量が小さいこと、避ける事ができない読み取り誤差などを考えると、数多くここに示したような振動たわみ形状が現れる事は、着目すべきと言える。振動たわみ形状とそれに対応する周期が0.3sec~0.4secに間に集中していることから、永代橋は、ここに示した波形がもっとも出現しやすいモードと判断した。自由減衰波を用いてモードと周期を求めた結果について、載荷状態縦列偏心走行で結果を表-1とそのモード図を図-10に、並列偏心走行を表-2とそのモード図を図-11に参考として示した。今回の実橋載荷試験実施にあたって、得られたモードには位相のずれが介在しているとは思うが、前述したような振動たわみ形状を永代橋の特性であると判断できたことは、とても興味深い結果である。なお、今回の載荷実験によって得られた永代橋の周期は、0.29sec~0.4secであった。
2-3 現行作用荷重に対して、耐力はどの程度あるのか?
大正12年12月に着工、満2か年の歳月を費やして大正15年12月に完成した永代橋は、前回示したように『復興局街路設計示方書』に基づいて設計・施工されている。その後、戦禍を潜り抜け約50年供用した後に行われた昭和44年における静的載荷試験(活荷重条件・TL-20)においても、十分な耐力を保有していることが明らかとなった。
しかし、現行の技術基準にある線荷重の規定は設計当初には無く、主載荷、従載荷の区別なしに一律に載荷していることや電車荷重を考慮しているため、一等橋としての活荷重による応力は設計当初の応力よりも小さくなっている。一等橋としての活荷重条件で再計算してみると、最大で許容応力度に対して92%程度の応力が発生していることが分かった。今回改めて、現行基準の作用荷重であるB活荷重を載荷した場合の断面照査を行ってみた。
断面照査は、常時断面力による断面照査を格子解析・断面計算で行うこととした。なお、耐荷性照査は、常時荷重に対して行っている。対象部材は、アーチ部(アーチリブ・主構、タイ、吊材)、床組(縦桁、横桁、横小桁)である。計算手法は、アーチ部は、主構造(アーチリブ・主構)を横桁と横支材等で接合した立体骨組でモデル化し、断面力を算出した。また、床組は、単純ばりでモデル化し、1-0法によって断面力を算出した。なお、T荷重は断面力が最大となる位置に載荷させ、横桁はアーチリブ・主構間で支持された単純ばり、縦桁は横桁間で支持された単純ばり、横小桁は縦桁間で支持された単純ばりとしてモデル化して算出している。今回再計算した永代橋の計算モデルを図-12に示したので参照されたい。
2-3-1 B活荷重に対する照査
①アーチリブ
アーチリブ頂部付近(部材番号1026)の座屈に対する安定照査においては、1.185(許容値1.000)となっており座屈耐力は超過している。なお、アーチリブの頂部は大正15年の設計図書においても程度は異なるが応力の超過が見られる(許容値に対して0.6%の応力超過)。部材1026に隣接する部材1025も同様で1.091と座屈耐力が超過している。これは、アーチリブの頂点から4番目の部材番号1023まで同様な結果となった。5番目以降、部材番号1009まで全ての部材は許容値の内に収まっている。なお、せん断に対しては、いずれの部材も許容値80N/㎟以内であった。表‐3にここまで説明した結果を示したが、赤に着色した部分が許容値を超えている部材、青に着色した部分が許容値内の部材である。
②アーチタイ
建設当時、先進的な材料と言える、英国海軍が使用した高張力鋼材・デュコール鋼を使ったアーチタイ材に着目したが、応力超過はなかった。しかし、アーチタイを繋ぐピン孔背面部の照査を行ったところ、応力超過していることが明らかとなった。なお、今回行ったピン孔の照査項目は、永代橋の設計当初においては当然行ってはいない。
③縦桁
床組構造の縦桁は、許容値に対して84%程度の応力超過である事が分かった。なお、計算結果を確認すると発生応に対する活荷重の割合は80%程度であった。
以上が、現行の作用荷重B活荷重で主要断面の応力を再計算した結果であるが、どのような部材が応力超過している分かり易いように図-13を示したので参照されたい。