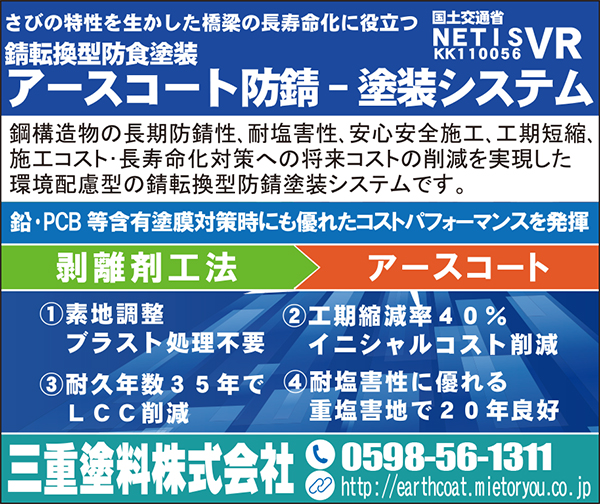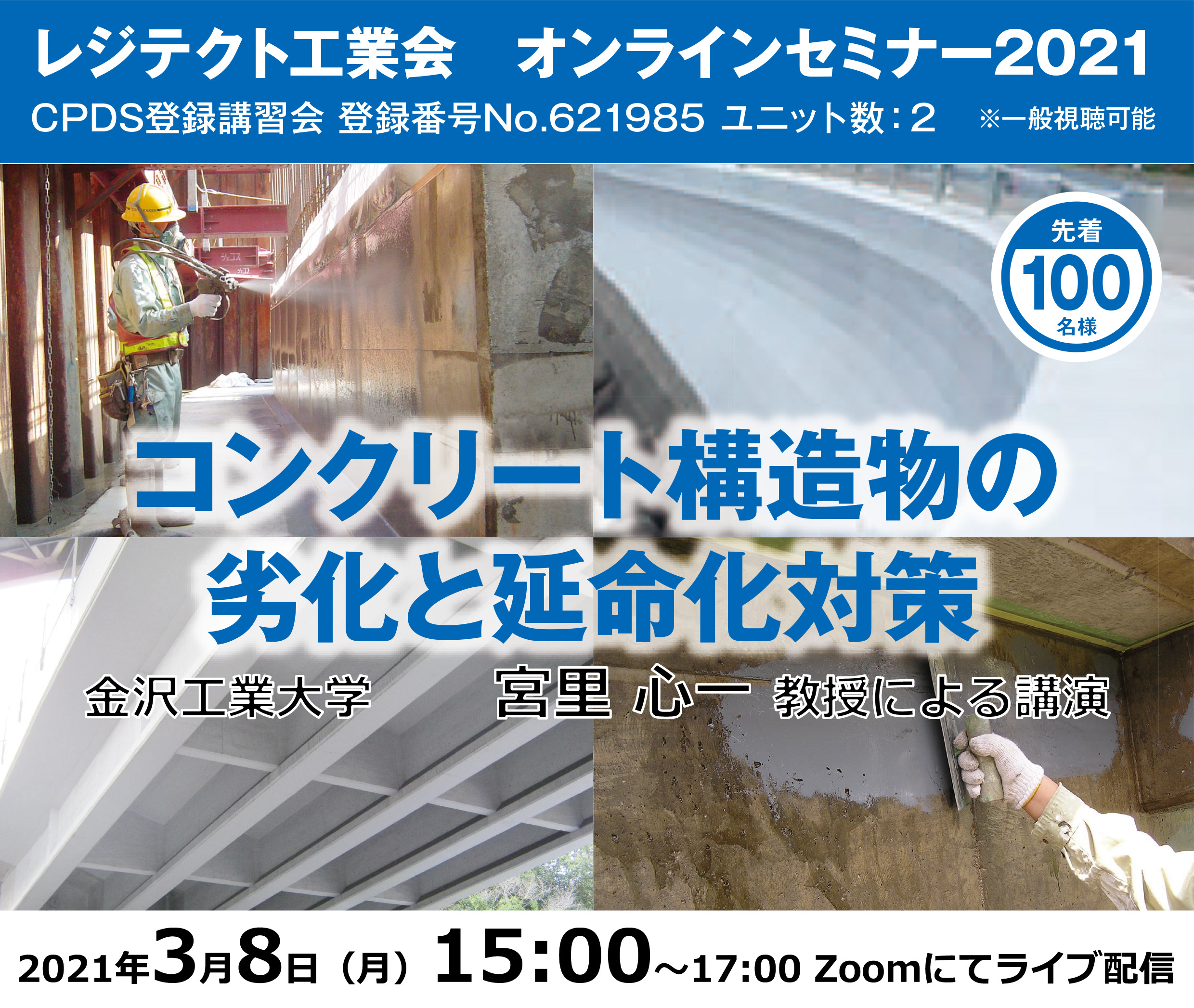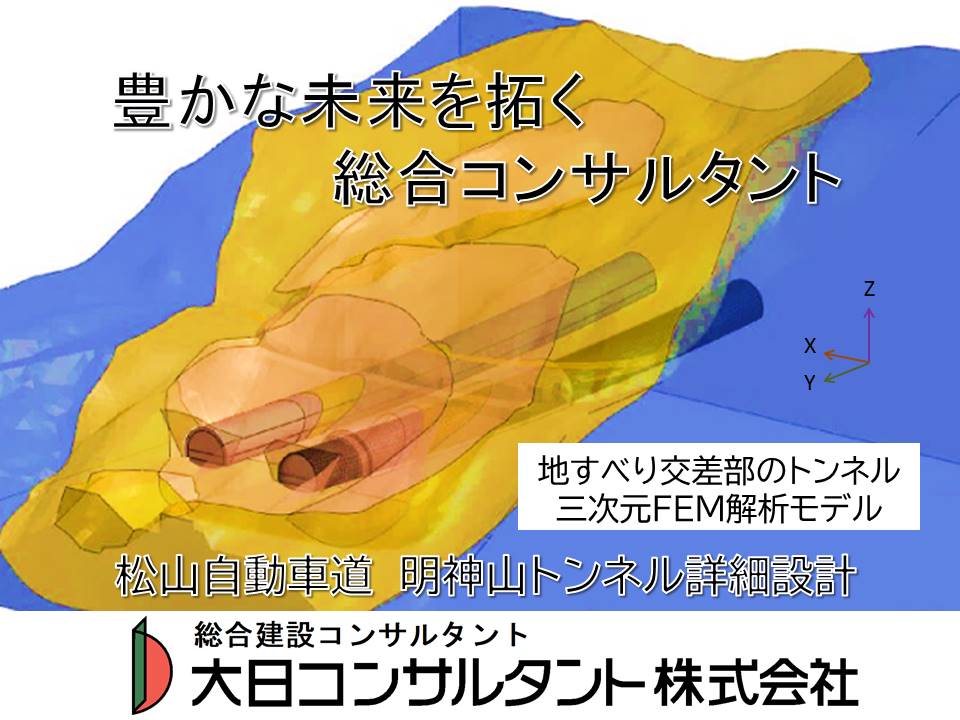-分かっていますか?何が問題なのか- 第57回 工学博士・鈴木俊男から学ぶこと ‐新たな構造形式を生み出す想像力と都市土木に必要不可欠な備え‐
これでよいのか専門技術者
1.はじめに
私の連載も今回で57回目となり、辛丑2021年(令和3年)になって最初の掲載である。私の連載で毎年恒例のように書いていた干支にまつわる四方山話であるが、四半期も終わる3月にもなるので止めておこう。それから、ここのところ毎回私独自のコメントを出していたCOVID-19関連の話も、読者の方々に耳にタコができていることや、待望のワクチン接種も始まったこともあり、読み飛ばされる可能性大なので止めておくことにした。
そんなことから今回、連載NO.57のスタートは何が相応しいかと思いめぐらす日々が数日続いた。私自身、何が題材として良いのか思案に暮れて1週間が経過、良い案も浮かばず床に着いてしばらく経った時、不意を突かれた地震(2月13日土曜日午後11時8分ごろ発生)に襲われ、家も心も大きく揺れた。過去の地震発災時には、携帯にダウンロードした緊急地震速報が数秒前に鳴っていたが、今回は何故か全く鳴らず、前触れなしの激しい地震動であった。私は寝込みであったこともあり、寝ぼけ眼で、とうとう来たか『令和関東大地震』と一瞬身構えた。私個人の感覚としては結構長く感じた揺れも、大きな横揺れを最後に徐々に治まり、私の思考回路にも多少ゆとりが出てきた。そうなるといつもの私、関係することは調べる探求心旺盛な自分に戻り、幾つかの地震関連ニュースを調べ始めた。
ニュースによると今回の震源地は、宮城沖でマグニチュード7.3、それも『東北地方太平洋沖地震』の余震とのことである。『東北地方太平洋沖地震』は、2011年3月11日午後2時46分に発生していることから、今回の地震は約10年経過した後の余震発生となる。2~3年内であるなら分かるが、10年も経って余震か?そんなことあるのか? と調べたところ昨年の3月既に、元東京大学地震研究所の都司嘉宣氏は、『東北地方太平洋沖地震』余震発生の可能性について次のように語っている。
 「東日本大震災は1000年に1度の地震と言われました。 三陸沖で同規模の巨大地震は1142年前の貞観11年(869年)に発生した貞観地震(図‐1参照)です。M8.4の海底地震によって生じた大津波が東北地方太平洋沿岸を襲い、壊滅的な打撃を与えたと記録されています。貞観地震発生後、9年経た元慶2年(878年)に震度6強〜7の貞観地震余震が関東地方を襲っていました」。
「東日本大震災は1000年に1度の地震と言われました。 三陸沖で同規模の巨大地震は1142年前の貞観11年(869年)に発生した貞観地震(図‐1参照)です。M8.4の海底地震によって生じた大津波が東北地方太平洋沿岸を襲い、壊滅的な打撃を与えたと記録されています。貞観地震発生後、9年経た元慶2年(878年)に震度6強〜7の貞観地震余震が関東地方を襲っていました」。
要は、『東北地方太平洋沖地震』発生後約10年経たとしても、大きな余震が発生する確率は高いとの発言であった。私は、地震の余震発生は数年程度の間と思っていたがそれは大きな間違いで、巨大地震の場合は十数年経て後でも発生するとの判断が地震学の常識のようだ。今回の余震、その基となる『東北地方太平洋沖地震』は海溝型地震であ る。海溝型地震とは、地球表面を覆う図‐2に示す各プレートの移動が主原因である。現状の探査技術では、年間わずか数㎝の動く各プレートの状態を精度良く把握することは可能であるが、プレート移動が起因となって発生する大地震が何時起こるかの予測は困難とのことだ。
る。海溝型地震とは、地球表面を覆う図‐2に示す各プレートの移動が主原因である。現状の探査技術では、年間わずか数㎝の動く各プレートの状態を精度良く把握することは可能であるが、プレート移動が起因となって発生する大地震が何時起こるかの予測は困難とのことだ。
忘れもしない今から20年前、三宅島・雄山が噴火し、災害復旧業務を三宅島島内で行っていた時、別の業務で三宅島に来られていた東京大学地震研究所の著名な研究員と話す機会があった。その時私は、国内の地震予知について、仕組みと可能性(発生確率等も)に触れ、聞いてみた。その時研究員は、「現状の技術では、地震予知は不可能です」と予知については素っ気ない答えであった。あれから20年、国内外の地震関連技術やICT技術(AIも含む)がこれだけ進歩しても、地震大国・日本の国民が強く望んでいる、肝心の地震発生予知が未だに困難とは、技術者の端くれとして私は、何とも残念な気持ちが一杯である。地震予知技術の開発には、日本の誇るスーパーコンピューター『富岳』を使っても駄目なのか。COVID-19感染に関する飛沫予測において、あれほど鮮明に再現できるのに残念だ。ここで、先の著名な研究員のプライドを保つために話すが、彼は次の巨大地震発生の確率が高いのは『東北、宮城沖周辺』、「10年前後に海溝型地震発生の可能性が高いですよ」と発言していた。『東北地方太平洋沖地震』が発生した時私は、真のプロフェッショナルとは控えめで奥深いが、実力は計り知れず、凄い予測力だと感心した。
話は変わり、震度6強の地震が発生しても鳴らなかった、我が国ご自慢の緊急地震速報システムの情報通信技術は正しく機能しているのであろうか?今回、私が体験した状況を思い返すと、さらに不安は増す。加えて、話題に上ることも少ない新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)が、こともあろうにOS(アンドロイド、ⅰOS)のバージョンアップに対応できていなかったとは、何とも情けない話である。国内のICT化については、「デジタル庁を設置し、世界のICT分野における最先端のポジションに!」の掛け声は立派だが、実態が全く伴っていない。日本の技術開発や技術者育成は口先だけで、日本の将来は本当に大丈夫なのだろうか。世界における日本のICT技術評価が右肩下がりの現状を、何とかしましょうよ!ICT業務に関係する専門技術者の方々。顧客である国民から、これまで創ったシステム全てに対し、「無用の長物である。投資の無駄」と厳しく査定されますよ。それもこれも最終的には、行政技術者の責任ですよ、お忘れなく。前置はこのくらいにして、それではここからが本題、鈴木俊男さんの世界に入るとしよう。
2.鈴木俊男と葛西橋その2
前回、私が尊敬する鈴木俊男さんのプロフィールと葛西橋の下部工について説明した。今回は、鈴木俊男さんが考案し、設計法から製作・架設工法までを自らで組み上げた葛西橋の上部構造について話をしよう。葛西橋上部工の構造形式は、主径間が鋼突桁式吊補剛桁橋、側径間及び取り付け道路が活荷重合成鋼桁橋である。主径間の3径間鋼突桁式吊補剛桁橋は、私の知る限り国内外に架設事例の無い形式と理解している。応用力学(建築では、構造力学と呼ぶ場合が多い)を学んだことの無い人や一般の人には、葛西橋は吊橋の一種と思っている人が多い様だ。
写真‐1は、葛西橋の全景(荒川河口部上空から撮影)と主径間部であるが、取り付け道路を含む橋長は何と約1.15kmにもおよぶ。主径間は、遠目で見ると自碇式吊橋に外観が似ているからか、連載で何度も登場した日本国重要文化財・清州橋と同形式かと見間違う。葛西橋に採用した突桁式吊補剛桁橋とは、ゲルバー式プレート・ガーダー橋の一種で、一般的なゲルバー式橋とは異なる中央支間の突桁(片持桁)部分が長い橋梁である。ここで、ゲルバー式橋について少し説明を加えよう。

2.1ゲルバー式橋とは
梁(はり)には、単純ばり、片持ちばり、ゲルバーばり、連続ばりなどに区分けされる。
ゲルバー式橋とは、ゲルバーばりを持つ橋梁を指し、図‐3に3径間ゲルバー橋のイメージを示すが、図でお分かりのように複数径間に渡って連続する主構造からなる橋梁である。海外では、カンチレバー形式(Cantilever Bridge:英文部分は田中豊講義録より引用。海外ではこのように呼ぶのが一般的である)と呼ぶのが一般的で、田中豊先生も大学講義(講義録より)の中ではゲルバー式ではなく、カンチレバー式と呼び構造詳細について講義している。また、カンチレバー式橋梁の場合、ヒンジを設ける箇所が中央支間の場合と 側支間の場合があるが、ヒンジが中央支間である図‐3では、単純桁部分を吊径間(Suspended span)、それを支えている部分を片持径間(Cantilever arm OR span)、側径間部分を定着径間(Anchor span)と呼んでいる。
側支間の場合があるが、ヒンジが中央支間である図‐3では、単純桁部分を吊径間(Suspended span)、それを支えている部分を片持径間(Cantilever arm OR span)、側径間部分を定着径間(Anchor span)と呼んでいる。
 主題とは離れるが、桁で下から支えているのになぜ吊桁と呼ぶのかその理由は、米国におけるカンチレバー式採用の橋梁実態から来ている。
主題とは離れるが、桁で下から支えているのになぜ吊桁と呼ぶのかその理由は、米国におけるカンチレバー式採用の橋梁実態から来ている。
米国の場合は、片持径間によってヒンジで両側を結ぶ径間を図‐4のように吊るタイプが多いことから、吊桁と呼ぶのだと私は教えられてきた。なるほど英単語の直訳、だから日本語で吊桁だ。このようなことから、私は米国のカンチレバー橋のほとんどがハンガーで吊っているものだ、と思い込んでいた。
時も経 て社会人になって渡米した際、現地でカンチレバー橋を見て回ったが、私の思い込みは大きく違っていた。米国のカンチレバー橋、桁形式の多くは、図‐4に示すようなハンガーで吊るタイプよりも図‐5に示すような、片持桁で吊桁を下から支えるタイプが圧倒的に多かった。
て社会人になって渡米した際、現地でカンチレバー橋を見て回ったが、私の思い込みは大きく違っていた。米国のカンチレバー橋、桁形式の多くは、図‐4に示すようなハンガーで吊るタイプよりも図‐5に示すような、片持桁で吊桁を下から支えるタイプが圧倒的に多かった。
私の安易な誤った思い込みに気付いたから言うわけではないが、読者の皆さん、海外に行って勉強しましょうよ、新たな真実を学ぶ機会が山ほどあるので。なお、図‐5の写真は、撮影時に私のミスでハレーションを起こしただけで、恨めしい気持ちを表す等の他意はない。カンチレバー橋の話が続くが、米国の道路橋で、吊桁を吊っている鋼製ハンガーが破断し事故を引き起こしそうになった状況に出くわした時がある。ハンガーが破断した当該橋は、発見が早かったからか何とか補修し、事なきを得ている。
 図‐6は、破断した鋼製ハンガーとピンを現場で抜き取り、それらを路上に並べて撮った貴重な写真である。
図‐6は、破断した鋼製ハンガーとピンを現場で抜き取り、それらを路上に並べて撮った貴重な写真である。
米国においては、私が現地で体験した鋼製ハンガー破断事故と同様な事故が各州で多発し、それ以降カンチレバー式橋の採用は無いとのことであった。カンチレバー式橋の採用を控える考えは、日本も海外も同様ではあるが、私は、他の形式にない、カンチレバー式特有の長所を活かす方法があるのでは、敢えてカンチレバー式採用に向けた研究や事例検討が必要なのではとも思っている。
2.2 ゲルバー式橋の特徴
ここで本題に戻すとしよう。ゲルバー式橋と連続桁橋との差異は、支点の不等沈下の影響を避ける目的でモーメントが0となる点付近にせん断力は伝えるが曲げモーメントを伝達しないヒンジを挿入することで、外的に静定な構造としていることにある。ここに示す理由から、ゲルバー式橋は、支点が多少沈下しても、ヒンジとローラーが変形に対応できることから、建設する地盤が悪い箇所に良く使われ、鋼橋だけでなく、当然コンクリート橋にも採用される事例が多かった。ここで話は少し脱線する。読者の方はお分かりと思うが、橋梁形式を考える場合、静定構造とすることが望ましく、不静定構造とすることは好ましくないと決めつけてはならない。何故ならば、不静定構造の方が静定構造よりも支点の反力数が多いことから、安全性が高くなる場合もある。その理由は、静定構造の場合、反力数や部材数を減らすと安定構造から、最悪の不安定構造になるからである。
私も誤解していたので、ここで必要なことを説明した。話しを戻して、既設橋を見たことが無い人にとっては、私が描いた先のイメージ図では分かりにくいので、写真‐2に3径間ゲルバー式鋼桁橋の事例として谷山橋を示す。また、図‐7は、写真‐2に示した谷山橋の架設状況である。図‐7を良く見てほしい、読者の皆さんが知らないと思う、昔の鉄筋コンクリート床版築造前の桁配置状況が分かる。また、ゲルバー構造が分かるように、側面部分を抜粋して示した。連続桁橋とゲルバー桁橋とは、伸縮継手数が違い、耐震性能や走行快適性能等の優位性から連続桁を採用するのが望ましいことは解っている。しかし、先にも話したように、私としては機会があれば、カンチレバー(ゲルバー)構造について再考してみたい。次は、いよいよ葛西橋に採用されたマニアックな上部工の構造形式について話をしよう。